入院診療のご案内

当科は2病棟78床を有する大学病院としては規模の大きい施設です。
一つの病棟は、精神科救急入院料(いわゆる「スーパー救急」)算定病棟で、34床(うち個室18床)あり、重症の精神症状があり治療の緊急性があり、さらに身体疾患も同時に治療することができる体制を整えています。他の医療機関では、受入れ困難なこうした患者さんを積極的に受け入れている精神科最前線の診療科です。
もう一つの病棟は、身体合併症・亜急性期病棟44床(うち個室12床)で精神科急性期医師配置加算を算定しており、精神・身体合併症につき院内各科と連携して診療にあたるほか、てんかんの長時間ビデオ脳波検査を積極的に行っている点が特色です。
当科は、埼玉県内の精神科医療救急医療体制において、身体合併症のある精神疾患患者さんの常時(24時間356日)対応施設として県内唯一の指定を受けています。
さらに両病棟とも、児童青年期や発達障害の入院診療、器質性精神疾患の脳波・画像検査、気分障害の光トポグラフィー検査や修正型電気通電療法(m-ECT)、治療抵抗性統合失調症のクロザピン治療、医療観察法の鑑定入院事例等、各種専門・特殊領域の症例を多々受入れています。
精神科医、認定心理士、精神科専門看護師、精神保健福祉士、精神科認定薬剤師といった多職種により個々の患者さんの検討会を毎週開催し、適切な入院治療を行うとともに、入院早期より退院後の家庭・社会へ円滑に復帰できるような診療体制を整えています。
充実の臨床教育体制の元で多彩な症例を経験できる稀少な施設となっています。
外来診療のご案内
当科外来は、一日約140人程度と院内最大規模で症例が豊富であることに加え、その内訳も統合失調症や気分障害、神経症性障害、認知症等にとどまらず、児童青年期や発達障害(自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症等)、てんかん等の特殊領域に至るまで幅広く、症例の多彩さについても特筆すべきものがあります。とりわけ、気分障害やてんかんについては高度に専門的な診療を展開しているほか、児童青年期や発達障害について段階的に経験をつめる体制を整えてきている点も当科の特色です。
力を入れている診療
精神科救急
精神科救急入院料(4階病棟)、精神科急性期医師配置加算(3階病棟)の施設基準をともに満たす大学病院としては稀有な施設です。精神科3次救急を含む重症かつ緊急性の高い症例に対応するのみならず、身体疾患も同時に治療できる体制を整えています。他の医療機関では受け入れ困難なこうした患者さんを、積極的に受け入れている精神科最前線の診療科です。入院期間の短縮にも努めており、4階病棟では90日、3階病棟では80日以内をそれぞれ目標とし、クリニカルパスを使用するなど最短で最適な入院治療を提供できるよう尽力しています。
これら精神科救急症例に対応するしくみの整備は、若手医師の臨床教育体制の充実につながっています。精神保健指定医は24時間常在しており、チーム診療制を採用しているため、どの時間帯においても臨床指導医が定まっています。充実の臨床教育体制のもとで、多彩かつ豊富な症例を経験でき、精神保健指定医・精神神経学会専門医のほか精神科救急学会を含む各種学会の専門医を取得することもできます。
てんかん診療
病棟には、長時間ビデオ脳波検査専用の個室があり、てんかん発作の精密な検査、正確な診断や非てんかん性疾患との鑑別を行っています。
てんかん専門医を中心に、他の診療科・多職種によるカンファレンスや勉強会を行いつつ、専門性の高いてんかん診療を提供しています。
また、てんかんに精神症状が生じることがありますが、当科では発作のコントロールばかりでなくこうした精神症状の安定といった両方の診断・治療が出来るのが強みです。これは、てんかん専門医かつ精神科医だからこそ可能となる治療です。
発作の消失が困難な難治の患者さんに対しては、当院てんかんセンターで連携している脳外科と共同で根治を目指すばかりでなく、たとえ発作を完全になくならなくてもその患者さんが求めるような少しでも良質な生活が送ることができるよう支援しています。
てんかん学会認定研修施設であり、てんかん専門医取得のための教育を行っています。専門医を目指さない若手精神科医もてんかん診療や脳波判読の基礎知識を一通り身につけることができるような教育体制をとっています。
双極症・
うつ病診療
松尾教授が専門外来を行っています。専門にしてきた長年の経験と最新の治療を組み合わせて、正確な診断および最適な治療の提供を心がけています。
双極性障害(躁うつ病)やなかなか良くならないうつ病(治療抵抗性うつ病)の患者さんのセカンドオピニオンも受けています。
修正型電気けいれん療法(mECT)や反復経頭蓋磁気刺激(rTMS)療法といった非薬物療法治療も積極的に行っています。当院のmECTは、麻酔科医師と共に、安全性の高い手術室にてこの治療を行っております。また、当院は埼玉県内で数少ないrTMS施行可能な施設です。rTMSは、入院にて1日40分、週5日、合計3~6週間行います。更に、急性期rTMSが有効だった場合に、その後外来で行う維持療法TMS(mTMS)(12か月間)を、先進医療(厚生労働大臣が承認した先進性の高い医療技術で、適応症と実施する保険医療機関が定められている)として実施することが可能です
鑑別診断補助検査のための光トポグラフィー検査を行っています。本検査施行に関して、いくつかの条件をクリアし正式に国から認可された県内第1号の施設です。そのため、この検査を安易な診断ツールとして用いるのではなく、松尾教授の長年のこの検査経験と合わせ正しい運用を心がけています。
小児精神疾患
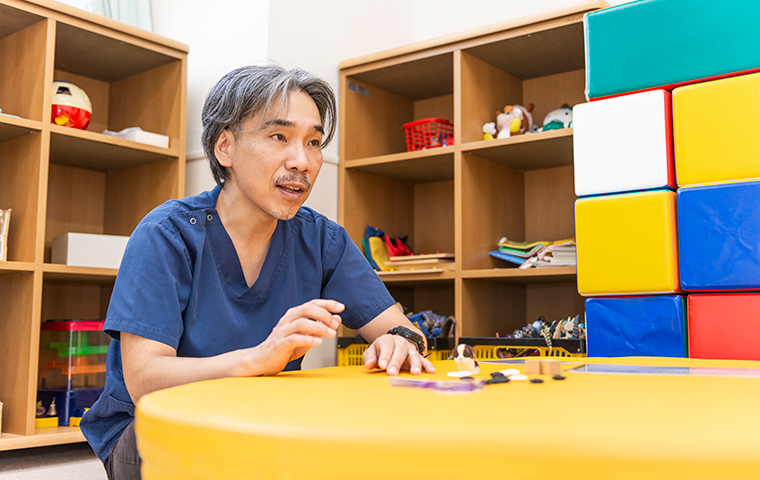
子どものこころ専門医による診療を行っています。「子どものこころ」を取り扱うとなると、診療の対象が不明確で範囲が不鮮明な印象をもたれることも多いのですが、当科小児精神部門では医療機関としての責任を果たすことを重視し、明確に小児精神疾患を診療の対象としています。対応する年齢は15歳、中学卒業までとしています。
世界標準の精神疾患の診断体系とされるDSM5あるいはICD11で定義された全ての精神疾患を取り扱い、エビデンスに基づいた標準的な診療が提供できるよう努めています。そのために日々、情報をアップデートし、心理療法・言語聴覚療法については新しい技法を積極的に取り入れています。また、自施設では実施できない技法については、学外の専門機関と連携し、トータルで標準的な診療が提供できるように診療ネットワークの構築を図っています。
当科は2022年の子どものこころ専門医研修の開始当初から研修施設群に認定されており、少なくとも精神医学的な観点では、国内で最良の臨床教育を行っていると自負しています。なお、小児精神疾患の診療及び臨床教育は埼玉医科大学病院神経精神科・心療内科だけではなく、同院小児科、埼玉医科大学かわごえクリニックでも実施しています。
老年期精神疾患

認知症を中心とした老年期における精神疾患を対象とします。認知症を呈する疾患は、アルツハイマー病、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などを代表に様々な疾患があります。認知症は行動心理症状として、妄想やうつ症状などの精神症状を呈することがあるため、精神症状の評価や対応が必要とされて精神科医療機関を受診される割合も高いです。老年期の精神疾患は認知症以外にも、うつ病、不安症、妄想性障害など多岐にわたり、身体疾患や心理社会的な要因も絡んでくるため慎重な評価や対応が必要です。老年期には身体疾患も合併している割合も高いため、身体疾患によっては早急な身体的治療が必要なケースもあります。身体疾患に対しては適宜身体科との連携を行っていきます。原因疾患の鑑別のため、大学病院である総合病院としての特徴を生かして、血液検査を適宜行い、神経画像検査(頭部MRI、脳血流SPECT、MIBG心筋シンチ、ドパミントランスポーターシンチグラフィー)などを必要に応じて行っていきます。精神科専門医による老年期特有な精神疾患の評価と、大学病院としての各身体科との連携が当科専門分野の特徴と言えます。